https://drive.google.com/file/d/1Om3yHI34nZMtkcMwG5QhNder0nMaFYwz/view?usp=drive_link
勢至菩薩 偉大な智慧の光を持つ菩薩
勢至菩薩
偉大な智慧の光を持つ菩薩

勢至菩薩(せいしぼさつ)とは?
正しくは大勢至菩薩といいます。智慧の光ですべてのものを照らし、人々を迷いや苦しみから救うとされています。大勢至菩薩と表記されることもあります。智慧とは物事のあり方を正しく見極める力・判断力を意味します。
阿弥陀如来の右脇侍として観音菩薩と共に三尊で表され、独尊で祀られることはほとんどありません。
浄土信仰の高まりとともに流行する来迎形式の阿弥陀三尊の場合、観音菩薩が死者の霊をのせる蓮台を持ち、勢至菩薩が合掌をする姿でつくられます。その姿勢は、立像・坐像のほかにひざまずいた姿の跪像もみられます。
ご利益
智慧明瞭、家内安全、除災招福のご利益があるとされています。午年の人々を守る守護本尊であり、午年に生まれた人々の開運、厄除け、祈願成就を助けるともいわれています。
勢至菩薩(せいしぼさつ)の像容
手を合わせているか水が入っている水瓶(すいびょう)を持っている姿が一般的です。
勢至
a

b

c

d

g
h
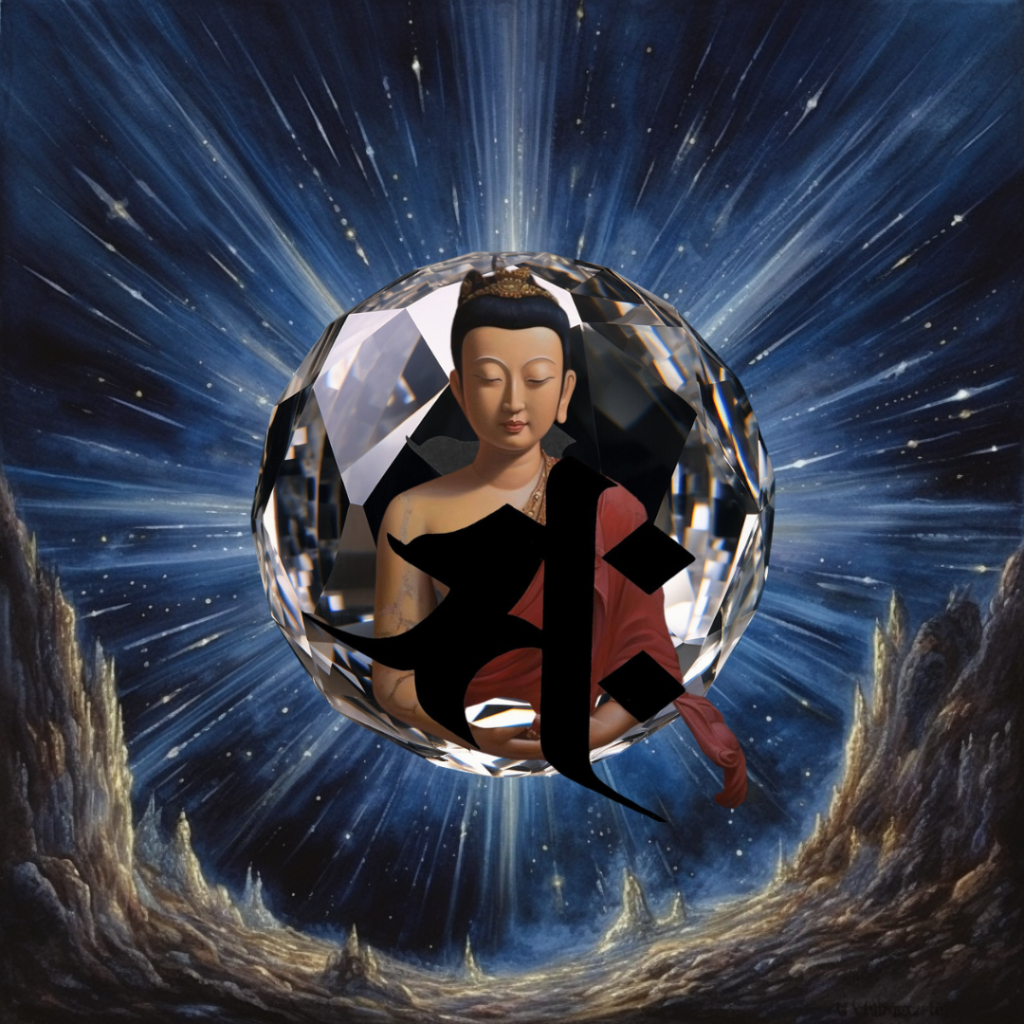
j
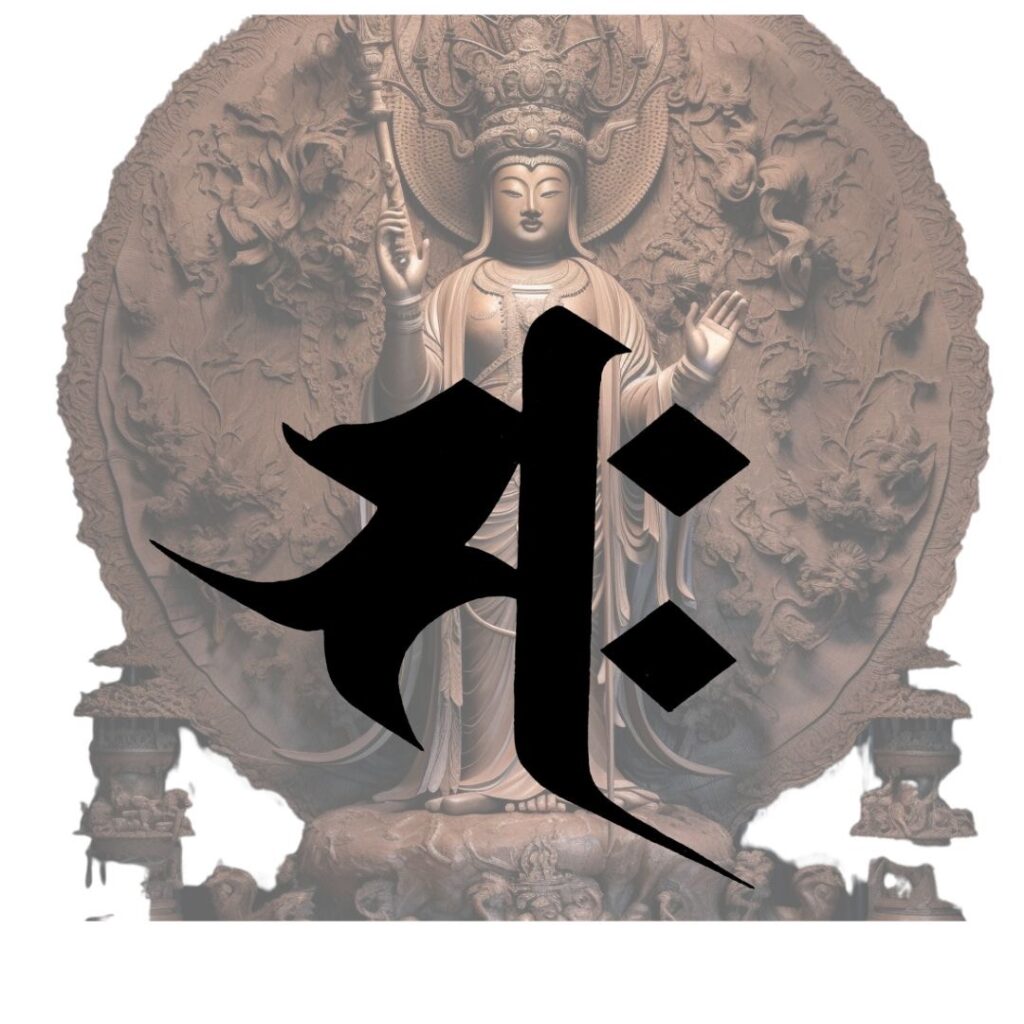
i

l

n
m
r]
]q
x
y
z
2024年4月24日 今日の運命 九星 無料 今日の運命
2024年4月24日
七赤金星の日
人より協力の依頼を受けたりする日。金運、喜び事あるも調子に乗って酒色に乱れぬよう心すべき日。小利に迷わず自他喜びを共にする心掛けも大切。
破壊の週 危の日
衝動的な行動には注意すべき日
危険なアクシデントに見舞われやすく、何かとトラブルに縁のある日です。勘違いや誤算、ちょっとした気の緩みから人とぶつかることも多く、何かにつけて空回りしてしまいます。些細なことからもトラブルに発展しやすいので、簡単なことでも十分に時間をかけて、気配りや気遣いを忘れずに行動しましょう。ビジネス面ではこの日の決断は大きな賭けとなりそうです。十分に検討を重ねたうえで、くれぐれも慎重に判断してください。専門知識を持った人への相談や関係各所への十分な根回しが必須です。
勢至菩薩(せいしぼさつ)、梵名マハースターマプラープタ (महास्थामप्राप्त [mahāsthāmaprāpta])は、仏教における菩薩の一尊。「大勢至菩薩」、「大精進菩薩」、「得大勢菩薩」の別名がある。現在日本では午年の守り本尊、十三仏の一周忌本尊として知られている。三昧耶形は未敷蓮華(ハスの蕾)。種子(種子字)はサク(सः saḥ)。
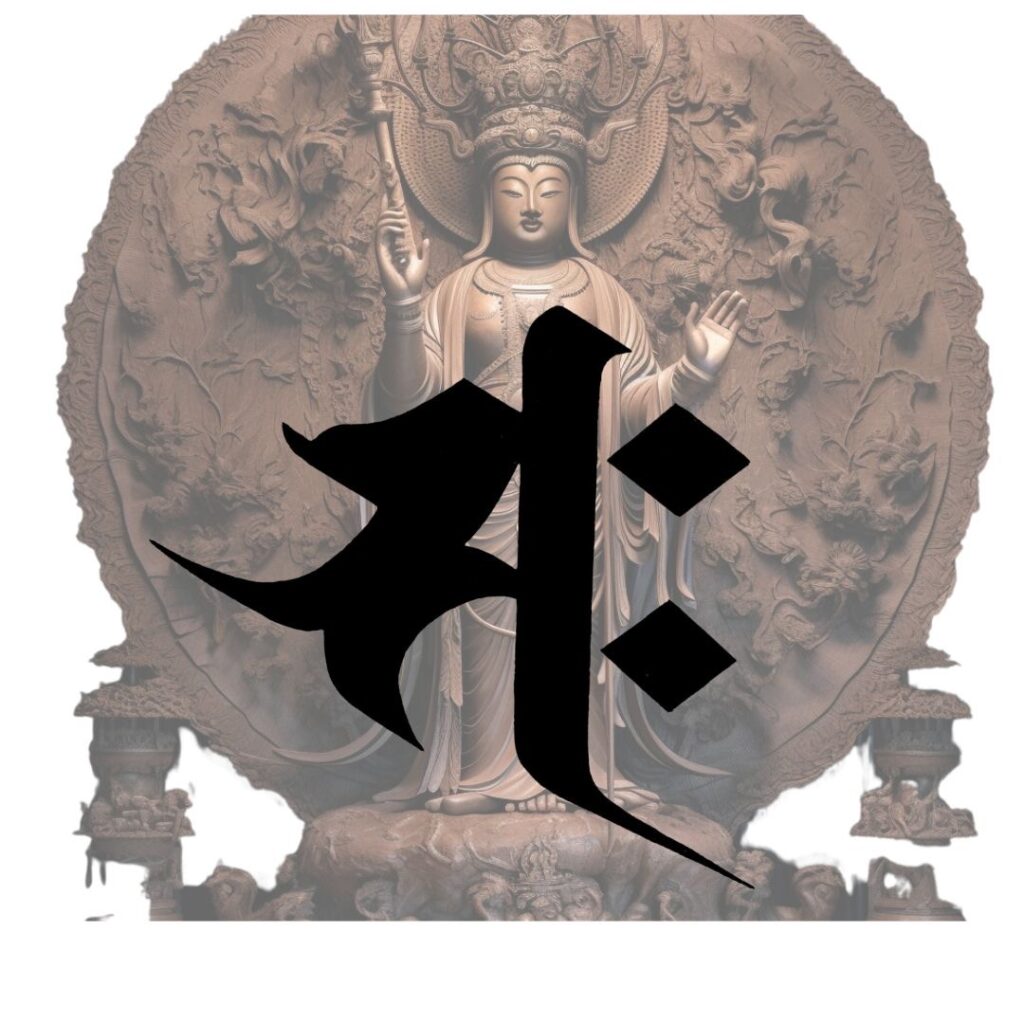
勢至菩薩
偉大な智慧の光を持つ菩薩
勢至菩薩(せいしぼさつ)とは?
正しくは大勢至菩薩といいます。智慧の光ですべてのものを照らし、人々を迷いや苦しみから救うとされています。大勢至菩薩と表記されることもあります。智慧とは物事のあり方を正しく見極める力・判断力を意味します。
阿弥陀如来の右脇侍として観音菩薩と共に三尊で表され、独尊で祀られることはほとんどありません。
浄土信仰の高まりとともに流行する来迎形式の阿弥陀三尊の場合、観音菩薩が死者の霊をのせる蓮台を持ち、勢至菩薩が合掌をする姿でつくられます。その姿勢は、立像・坐像のほかにひざまずいた姿の跪像もみられます。
ご利益
智慧明瞭、家内安全、除災招福のご利益があるとされています。午年の人々を守る守護本尊であり、午年に生まれた人々の開運、厄除け、祈願成就を助けるともいわれています。
勢至菩薩(せいしぼさつ)の像容
手を合わせているか水が入っている水瓶(すいびょう)を持っている姿が一般的です。
正位置・・・目覚め。驚異。変革。著しい変化。目的の完成。不滅の精神力や信仰。思想を身につける。成功。再生。回復。蘇る愛。母性愛。
逆位置・・・不安定。精神力の欠如。未決定。延期。愛の幻滅。優柔不断。別離。あざむき。
正位置・・・位置の変化。更新。結果。他の解釈によれば、訴訟における損失。
逆位置・・・弱さ。無気力。単純。慎重。決心。判決。

| 04月24日 (水曜) | |
|---|---|
| 月齢 15.3 |
 |
| 潮汐 大潮 |
|
月名(旧暦日)
十六夜月
http://cyber-price.com/buddha/
Buddha Japan journal
日本の仏教を発信しますSend Japanese Buddhis
日本の仏教を発信しますSend Japanese Buddhis sサイト
大日如来の智慧を表現した「金剛界」 .一印会 “Kongokai” expressing the wisdom of Dainichi Nyorai.Ichiinkai
胎蔵界曼荼羅 たいぞうかい Womb Realm Mandala Taizokai
瞑想のcyber–price
デジタル 健康 PC カメラ 家電
因縁の成り立ち

前に解説したところでは三人分の頭蓋骨が登場し、それぞれの性別・死因 死後の行き先につ
いてミガシラバラモンが答えました。 一人目は多くの病を併発して全身が痛んで亡くなった男性 で、死後は三悪に堕ちていました。 ここでは三悪趣と表現されていますが、要するに地獄界・ 餓鬼・畜生界のいずれかに生じたということですね。 二人目は産厄で亡くなった女性で、死後 畜生界に生まれていました。三人目は飲食の過多による下痢で亡くなった男性で、餓鬼界に生まれていました。いずれも因縁によって良くない亡くなり方をしているので、死後も悪趣の境界 で苦しんでいたわけです。
ところで、地獄界・餓鬼・畜生界に生じたという表現には、二通りの解釈が考えられます。 まず、人は、死後に「中有」(死んでから次の生を受けて生まれ変わるまでの中間的在り方)の世界 に入りますが、ほとんどの人は死後、意識が戻ると、そこから阿鼻野街道(死人街道・亡者街道) を通ってサイの広場へと向かいます。そしてサイの広場にある断崖絶壁から三途の川(三瀬川) に堕ちます。 その時、業の重さによって一番手前にある地獄界、中央にある餓鬼界、一番遠くに ある畜生界に通じる三つの瀬のいずれかに堕ちて、生前の罪をつぐなうために、急流によってそ れぞれの世界に運ばれたということです。
もう一つは、それぞれの世界で罪をつぐなってから冥界に到着し、そこからこの世界に転生し た時に、その因縁による環境や運命が、地獄界・餓鬼・畜生界のいずれかの境界であるとい うものです。
これをわたくしの著書『人はどんな因縁を持つか」(阿含宗教学部)と行
出版部)から引用敷衍すると、たとえば地獄界の境界では、次のような因縁によって苦しみま す。
自殺、他殺、事故死のいずれかに遭うという「横変死の因縁」。心がけの善い悪いにかかわら ず、刑事事件を起こして刑務所につながれる「刑獄の因縁」。恩を受けた人(主人、師、上長、取 引先 先輩など)をだましたり、傷つけたり、とにかく相手になにかしら損害を与えるという 「逆恩の因縁」。この逆の因縁の場合、性格としては、恩を仇で返すというようなものと反対に、 心に恩義に報いようとする心がけを持っていて、そのように努力をしながら、かえって結果的 には、その恩義を仇にして返すようなことになってしまうことがよくあります。だいたい、自分 にとって恩義のある人というのは、自分に好意を持ち、あるいは信用して、自分を引き立て、力 になってくれる人です。 こういう相手に、無意識とはいえそういう損害を与えたり、背いたりす るということは、自分で自分の手足をもぐことです。 自分の有力な味方を失うことになります。 そこで孤立無援となって、人生の失敗者となってゆきます。
また、肉親の者同士、血縁者同士が、互いに運気生命力を損ねあい、傷つけあって分散して ゆく「肉親血縁相剋の因縁」。
そういった因縁に苦しみます。
また、餓鬼界の境界では、次のような因縁に苦しみます。
必ず癌になるという「癌の因縁」。家の運気が次第に衰えてきている家系に生まれるという「家運衰退の因縁」。 これは、実力がありながら、妙にめぐり合わせが悪く、ウダツが上がらず、
年を取るほど運気が衰え、生活が悪くなっていくというものです。
そして、この因縁から出てくるのが、なにをやっても、一応、七、八分通りまでは順調に進む が、あともう一、二分というところで必ずダメになる、決して実らないという「中途挫折の因 縁」などです。
畜生界の境界に生まれると、次のような因縁に苦しみます。
目がつぶれて失明したり、手足を断つ、というように、肉体に障害を受ける「肉体障害の因 「縁」。つまり、けがの因縁で苦しみます。 また、精神病や頭部のけが、 または脳溢血、脳軟化症 等の病気で苦しむ、あるいは程度の軽い因縁の人は年中、頭痛、肩こり、不眠症などに悩まされ る「脳障害の因縁」などです。
これらの因縁についての詳細は、『人はどんな因縁を持つか」をお読みください。
地獄界に堕ちた人たちのありさまは、わたくしが霊視した結果の一部を著書 『守護神を持て」 や 『輪廻転生瞑想法I』(ともに平河出版社)などで紹介しましたが、餓鬼界では、飢えや渇きに 苦しみます。 同時に浮浪霊となってこの世をさまよっている餓鬼もおります。
阿含宗では、毎年、盂蘭盆会万燈先祖供養を行なっておりますが、 万燈のほかに必ず精霊棚と いうものを境内の暗い一角に設けて供養しています。 これは「施餓鬼供養」 つまり、 餓鬼の供養 のためなのです。餓鬼とは、日本の昔の絵巻物の一つである『餓鬼草子』に描かれているように、 皮膚が骨に張りついたように痩せこけて腹部だけが異様に膨れているという醜い姿で、いつもこ そこそと暗い隅に隠れて、餓えと渇きに苦しんでいる存在です。 わたくしの霊視では背丈は小さ く、三十~四十センチほどです。 彼らは自分の姿の醜さを知っているので、それを恥じて人前に
は出たがりません。 そこで境内の一角に暗い場所を造り、そこに特別に法を修したお供えをして 供養しているのです。 彼らは特別に法を修したお供物でないと口に入れることができません。 また、畜生() に生じるという場合、畜生界に堕ちて罪をつぐなったり、 この世界で畜生界 の境界に生まれ、その因縁に苦しむということのほかに、本当に、犬や豚や鶏に転生してしまう 場合があるのです。わたくしの霊視によると、死後、サイの広場に向かう阿鼻野街道の途中で、 生前自分に恨みを持っていた者に甘言で誘われることがあるのです。その死者は顔が生前とは変 わっているので、自分に恨みを持っていた相手だとは気がつきません。 誘いに乗ると大きな洞窟 に案内されて休むように勧められます。そこでうとうとしたかと思うと、目がさめると豚になっ ていたり、犬になっていたりするのです。





