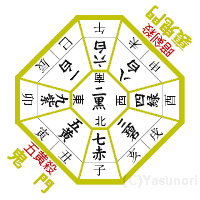普賢 ― 遍く歩む者
Samantabhadra — The One Who Walks Everywhere
夜明け前 名を持たぬ刻
地の奥で 足音が目を覚ます
白き象が 闇をほどき
世界は 静かに息を思い出す
Ong Sanmaiyya Satvan
ओंग सनमैय्या सतवन
遍く歩め 遍く賢く
知るためじゃなく 行くために
剣は誓い 杵は祈り
立ち止まらぬ意志が 道になる
遍く歩め 遍く今を
Ong Sanmaiyya Satvan
ओंग सनमैय्या सतवन
声なき祈りの ただ隣へ
問いに答えず 背を向けず
オン・サンマイヤ・サトバン
Ong Sanmaiyya Satvan
ओंग सनमैय्या सतवन
Before the dawn, in a nameless hour
From the deep of the earth, footsteps awaken
A white elephant parts the veil of night
The world softly remembers how to breathe
Ong Sanmaiyya Satvan
ओंग सनमैय्या सतवन
Walk everywhere, be wise in all things
Not to know, but to go
The sword is a vow, the vajra a prayer
An unyielding will becomes the path
Walk everywhere, walk this very now
Ong Sanmaiyya Satvan
ओंग सनमैय्या सतवन
Beside the voiceless prayers
Turning neither away nor back
On Sanmaiyya Satvan
Ong Sanmaiyya Satvan
ओंग सनमैय्या सतवन
。