不動明王
不動明王
https://www.canva.com/design/DAGzZxOoTTs/VkmbJ9AeiYLsffZBJ81t_w/watch?utm_content=DAGzZxOoTTs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h7bad231506
2017.12.25
こんにちは!ハチハチ編集部やよいです。
いよいよ年明けも間近に迫ってきましたね〜。
みなさんはどんな正月を過ごしますか??
私は厄年というわけではないのですが、初めて厄除けに行ってみるつもりです。お布施を祓うような厄除けをしたことがないので、ちょっと楽しみ?です( ^ω^ )
さて、お正月の行事ごとの中でも、忘れてはいけないのが「初詣」

初詣ってだいたい行くところ決まってますよねー。
「昔から決まったところで参拝」か、
「とりあえず有名そうな所に行ってみる」
というのが多いんじゃないかと思います。
でも結局感じるのは
ということ。
私たちは生まれつき仏様とご縁が結ばれていますが、その一生を守ってくださるのが守護仏です。この仏様は干支によって違い、自分の仏様を信仰するとご加護がもらえることがあります。ぜひ自分の守護仏を知ってそのお寺の初詣に行ってみてください。
今回は干支別に守護仏をご紹介しちゃいます!
あなた守ってくれる仏様はいったい誰でしょうか??

千本の手を持ち、あらゆる人の願いや苦しみを救うため、33通りもの姿に変化します。千の手であらゆる願いを叶えてくれる慈悲深い菩薩様。
真言「オン バサラ タラマ キリク」

宇宙のような無限の知恵と慈悲の心をもつ菩薩様。人々の願えを叶えるために蔵から知恵や記憶力、知識取り出してを与えてくれるとされています。
真言「ノウボウ アキャシャ キャラバン オン アリキャ マリボリ ソワカ」

「三人寄れば文殊の知恵」ということわざでがあるように、知恵や学問をつかさどる菩薩様。物事のあり方を正しく見極める力・判断力を意味する「智慧」を司っています。
真言「オン アラハシャ ノウ」

深い慈悲の心と知性で、人々を救ってくれる賢者の菩薩様。頭が4つある像に乗り延命の徳を備える。減罪においては罪を告白する勇気を授け、罪を消してくれるといわれています。
真言「オン サンマヤ サトバン」

知恵の光で世の中を照らし、人々を苦しみと迷いから救い出してくれる菩薩様。大勢至とも言われその威力は凄まじく、智慧を司り、人の善を護ります。
真言「オン サンザンサク ソワカ」

神仏習合の解釈では天照大神とも同一視される、宇宙の根本を司る如来様。真言密教の教主で、この世のすべてを照らし、癒しと繁栄を与えてくれる。大日とは「大いなる日の輪」という意味。
真言「オン アビラウンケン バザラ ダトバン」

破壊と恵みの相反する面を持ち合わせる明王様。邪悪な心を断ち切り、煩悩を抱えるすべての民衆を仏の道に導く。憤怒の表情だがとても慈悲深い。
真言「ノウマクサンマンダ バザラダン センダ マカロシャダ ソワタヤ ウンタラタ カンマン」

人々をあらゆる苦難から救い極楽浄土へと送ってくれる如来様。西方にある極楽浄土の主で、限りないの光と限りない命で、人々を救い続ける。
真言「オン アミリタ テイセイ カラ ウン」
みなさんの守護仏はわかりましたか?
初詣に自分の干支の仏様にお参りして運気をアップしましょう!♪
ちなみに、家族の干支がバラバラで困った〜って方は守護仏が全員いらっしゃるお寺もあるのでまとめてそこへ行くのもいいかもしれません。
・総本山善通寺(香川県善通寺)…お砂踏み道場
・出釈迦寺(香川県善通寺)…干支別お守り本尊
「子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)」の12種の動物で構成され、もともとは中国で生まれた暦や時間を表す方法です。現代では、年賀状などで年を表すものとして広く親しまれています。
![]() 十二支占い
十二支占い ![]()
言わずと知れた十二支占いです。
自分の十二支の性格を調べて見るもよし、ご利用者や同僚・管理者の性格を調べて
みるもよし、活用はお任せします。
いろいろな意味での、コミュニケーション材料になるかと思います。
⇒『十二支占い』の資料をプリントする
十二支の見方
十二支占いでみる節代わりは、『2月4日』になります。
従って2月3日までに生まれた方は、その前年の干支となります。
干支の豆知識
誕生「月」の十二支 (十二支) (月)
子 12月
丑 1月
寅 2月
卯 3月
辰 4月
巳 5月
午 6月
未 7月
申 8月
酉 9月
戌 10月
亥 11月
「還暦(かんれき)」とは?
| (基本の性格) 頭が良く、知的好奇心を強く持っています。また新たな発想力や企画力も豊富です。 ただしその好奇心旺盛な性格上、落ち着きに欠け、興味があることにはじっとしていられません。 基本的資質として、几帳面できれい好き、細かなことに気が付くデリケートな性格の持ち主です。 目標には努力を惜しまず、コツコツと精進し、いずれ達成する強運を持っています。 柔軟性や強調性があることから、どんな環境にも適応できます。 不平不満をあまり顔に出さず温厚ですが、内面的は強引な性格を持っています。 若い頃には苦労も多いですが、中年期以降から晩年は安泰です。 家系の衰えを守る宿命をもっているようです。(仕事) 商才があり、組織に属するよりも独立自営の方が活躍できます。 若い頃は職が定まらずに転職を繰り返すこともあるようですが、適職を得れば集中して大きく発展します。 努力の積み重ねで人の上に立ち、活躍する方が多いようです。 (お金) (恋愛) (病気) |
⇒上に戻る
うし年 (丑) 【守り本尊…虚空菩薩】 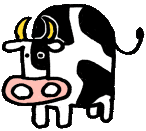
| (基本の性格) 責任感が強く、努力家で根気強い性格を持っています。 思考能力は高いのですが、自己表現があまり得意ではありません。 外見からは一見のんびりとして内気な性格のように見えますが、実は神経質で強情な性格の持ち主です。 こうと決めたらてこでも動かないため、場合によっては頑固者・偏屈者と見られる場合もありますので注意が必要です。 本来、愛情豊かで人情派の性格ですが、好き嫌いがはっきりしている性格のため、人と衝突してしまう事もあるようです。 若い頃には苦労もしますが、中年期以降には運気が安定します。(仕事) 安定した職業に向いていますが、職人的な気質もあるため、美術や建築関係の仕事も適しています。 転職には向いていません。(お金) 無駄遣いは好まず、倹約家です。一攫千金を望むと失敗しますので注意が必要です。(恋愛) 自己表現があまり得意でないこともあり、恋愛は上手ではありません。 |
⇒上に戻る
とら年 (寅) 【守り本尊…虚空菩薩】 
| (基本の性格) 義理人情に厚い、親分肌な性格をもっています。 また勇気と冒険心も旺盛で、新しいことにもひるまずに向かっていく積極性があります。 ただし反面、謙虚さに欠け、言い出したら後には引かない強情な面を持っています。 人との衝突時には怒涛のごとく相手を脅かすような場面もあるかもしれません。短期にはくれぐれも注意しましょう。 一見、楽天家なようですが、実のところ環境の変化には弱く、些細なことで挫折してしまう事もあるようです。(仕事) 義理人情に厚く、行動派の性格を生かして、人に奉仕する仕事をすると大成します。 親分肌の性分のため、気前良くふるまって散財することが多いようです。(恋愛) 情熱家で一途な性格ですが、相手の心情を思いやる面に欠ける場合がありますので気をつけましょう。(病気) 循環器、呼吸器、消化器系の疾患には注意しましょう。 |
⇒上に戻る
うさぎ年 (卯) 【守り本尊…文殊菩薩】 
| (基本の性格) 温厚・社交的で愛嬌もあるため、誰からも愛されます。 争いごとを嫌うため、強引な態度や発言は少なく、人を和ませる性格をもっています。 周囲の人から信頼され、上の人から引き立てられることも多いようです。 おおらかな性格の反面、物事をやりっぱなしにする事がありますので、責任感を持つ事が大切です。 中年期には、冒険心や野心から失敗することがありますので注意してください。 (仕事) 外交的な性格を生かした職に適しています。 美術的なセンスを持ち、組織でも自営でも活躍できます。 野心や大望が少ないため、目上からは引き立てられる存在になるようです。(お金) 社交的な性格から、経済的苦労は多くなります。 性格上、恋愛は早熟タイプです。 肝臓病、呼吸器疾患に注意しましょう。 |
⇒上に戻る
たつ年 (辰) 【守り本尊…普賢菩薩】 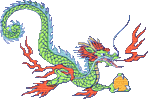
| (基本の性格) 何事にも積極的に前向きで、小さなことにはこだわらない性格です。 周囲からは頼られ、いつの間にかリーダー的な存在になっていることが多いようです。 直感力や集中力も優れており、行動力は人並み以上です。 ただし冒険やロマンに憧れをもつ、夢多き性格を持っているため、ときに理想と現実とのギャップに苦労する場合があります。 表面的には物静かで、一見温厚に見えますが、内面は短期で負けず嫌な面をもち合わせています。 自分で判断して行動することを好み、命令されることを嫌います。 プライドが高く、わがままな面を持っていますので、人間関係のトラブルには注意が必要です。 早くからチャンスに恵まれますが、性格的に気まぐれな事があり、せっかくのもっている才能を発揮できない場合があります。根気と忍耐力を持つようにしましょう。(仕事) 芸術面や専門的分野に優れた才能を持っています。 干渉されることを嫌うため、自営業の方が向いているかもしれません。 (お金) (恋愛) (病気) |
⇒上に戻る
へび年 (巳) 【守り本尊…普賢菩薩】 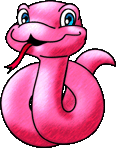
| (基本の性格) 習慣や伝統にとらわれない自由な発想を持ち主で、困難に屈しない、強い精神力を持っています。 貪欲なまでの向上心があり、ときには実力以上のことにも挑戦してしまう場合があります。 辛抱強い勤勉な性格ですが、行き過ぎると諦めが悪い執念深い性格に変わってしまう場合もあります。 何事にも見切りは必要でしょう。 勤勉な姿勢とその感受性の豊さで、周囲からの信頼は厚く、いずれ人の上に立てます。 ただし本来もつ思慮深さ、用心深い性格から、ともすると猜疑心が強く現れてしまう場合がありますので注意しましょう。 気品高く、虚栄心が強い性格上、人に使われることを嫌います。暴力や争いごとも好きではありません。 若い頃には変動もありますが、粘り強さと強い精神力をもっていますので、中年期以降に成功する方が多いようです。 十二支の中ではもっとも幸運を持ち合わせているといわれています。(仕事) 知性を生かした職業が向いているようで、独立自由業の方が多いようです。 お金は基本的に不自由しませんが、見栄や虚栄からの浪費が多くなるため注意が必要です。(恋愛) 嫉妬心が強く、恋愛は波乱含みとなりそうです。(病気) 神経系、消化器系の疾患、関節、筋肉痛など注意しましょう。 |
⇒上に戻る
うま年 (午) 【守り本尊…勢至菩薩】 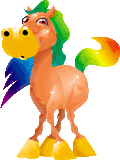
| (基本の性格) 開放的で陽気な性格のため、誰とでもすぐに仲良くなれます。 派手でにぎやかな事を好み社交的です。 生命力がおおく負けず嫌いな面があり、いろいろな事に積極的に挑戦しますが、若干根気が足りない傾向にあります。 大雑把で、細かいことは苦手です。 義理人情もあまり好きではありません。 本人に悪気はないのですが、短気で礼儀に欠ける面があるため、周りを不快にさせてしまう場合がありますので注意しましょう。 午年の方は、そのバイタリティーを生かして、中年期までに人生の基盤を作ることが成功の秘訣となります。(仕事) 芸術や芸能関係、教師などが適しているようです。 (お金) (恋愛) (病気) |
⇒上に戻る
ひつじ年 (未) 【守り本尊…大日如来】 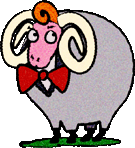
| (基本の性格) 従順で温和、情に厚く親切です。人との争いや対立を嫌うため、人間関係もいたって良好です。 ただしその優しい性格から頼みごとが断れない場合もありますので注意して下さい。 性格は、正直第一で曲がったことを好みません。 また思慮深く慎重な性格ゆえ、行動力に欠ける場合があり、周りからは優柔不断と思われる場合もあります。 一見のんびり家に見える未年ですが、実は気配りや世の中の動きを先取りする才能を持っています。 また見かけによらず芯が強く、地道な忍耐力も持っています。 若い頃は回り道も多いようですが、努力家なので中年期以降には運気が上昇します。(仕事) 芸術面に秀でて独自の世界観を持っていますが、消極的な性格のため、その才能が埋もれがちとなってしまいます。 金運は恵まれています。 結婚願望は強いのですが、おくてな性格のためチャンスを逃しがちとなってしまいます。(病気) 神経疾患、アレルギー疾患には注意しましょう。 |
⇒上に戻る
さる年 (申) 【守り本尊…大日如来】 
| (基本の性格) 明朗活発で機敏性・柔軟性に富み、常に前向きな姿勢を持っています。 また手先も器用で、才能豊かな方が多いことも申年の特徴です。 性格的には、聡明で統率力もあり、冷静な判断と実行力に優れています。 巧みな話術と気配り上手で、若い頃から目立つ存在となります。 ただしその頭の回転の速さが、ともすると軽率で自信過剰なイメージとなる場合もあります。 気を長く持ち、即断即決を求める姿勢は控えていきましょう。 クヨクヨしない明るい性格は、ときに楽観的で飽きやすい人と思われてしまいますので注意が必要です。(仕事) 机の上の仕事よりも、人とかかわりある仕事に適しています。 転職等はあまりしないほうが良いでしょう。 (お金) (恋愛) (病気) |
⇒上に戻る
とり年 (酉) 【守り本尊…不動明王】 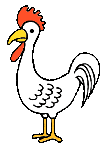
| (基本の性格) 人当たりが良く、愛嬌があります。 社交的で、色採感覚に優れているため、とてもおしゃれです。 性格は、几帳面で仕事熱心。 また頭の回転が速く思考力が優れています。 ただし、せっかちな面があり、ともすると自己中心的に物事を行おうとしてしまうため注意が必要です。 計画的で無駄を嫌う徹底的な効率家なので、現実的な性格といえます。 時には、保守的で、かたくなにルールを守ろうとする面も見られるようです。 若い頃は何事にも飽き易く、長続きせず浮き沈みがありますが、中年期以降から才能が開花し運気も向上します。 ただし大望は失敗が多いの注意しましょう。(仕事) どんな仕事でもこなせる器用さを持っています。 若い頃は浪費傾向にありますが、本来計画的な性格であり、徐々に財は安定してきます。(恋愛) 魅力があり、異性には持てるタイプです。(病気) 呼吸器系、内臓関係には注意しましょう。 |
⇒上に戻る
いぬ年 (戌) 【守り本尊…阿弥陀如来】 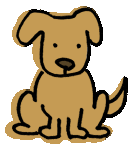
| (基本の性格) 正義感に強く、まじめで正直な性格です。 また義理堅く、忠誠心が強いので、いったん信じた相手は自分からは裏切りません。 一見明るく人懐っこい性格ですが、まじめさゆえに融通の利かない頑固な面も持ち合わせています。 責任感が強く、規律厳守な性格のため、目上の人からは信用されます。 時に、状況分析に欠け、判断を誤る場合がありますので、一人よがりにならないようにしましょう。 中年期以降は、周囲からの引き立てもあり運気が向上していきます。(仕事) 職務に忠実な努力家で、組織において活躍します。 自ら上に立つよりも、信頼できる上司のもとで力を発揮する存在です。 (お金) (恋愛) (病気) |
⇒上に戻る
いのしし年(亥) 【守り本尊…阿弥陀如来】 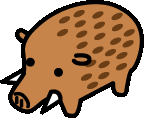
| (基本の性格) 飾り気なくさっぱりとした天真爛漫な性格で、思いやりと包容力を持っています。 誠実で信義にも厚く、協調性もあります。 何事にも自信をもって挑戦し、周囲を引っ張っていく力があります。 しかし反面、いったん思い込むと後先を考えず行動してしまい、損をしたり迷惑をかけたりする場合があります。 一呼吸し、人の意見を聞き入れるようにしましょう。 はつらつとして剛気がみなぎる亥年ですが、意外に情に弱く、涙もろい面があります。 若い頃の猪突猛進傾向も、中年期以降には少なくなり、運気は向上し実力を発揮します。(仕事) 能力や個性を生かせる職業に向いています。 サラリーマンにも向いており、会社では欠かせない存在になります。 専門職や自営業にも向いていますが、共同事業は失敗の元になりますので注意しましょう。 (お金) (恋愛) (病気) |
オロチと二龍王
Orochi and the Two Dragon Kings
荒ぶる水よ 山を覆い
娘を奪う 紅の眼
剣を振るう 神の声
稲田を護る 祈りの灯
namaḥ sarvatathāgatānāṁ
apratihata-jñānābhiṣekebhyaḥ
oṁ ca le cu le cundī svāhā
Draco Rex Nanda et Draco Rex Upananda
オロチ沈み 雨は舞い
二龍王よ 雲を招け
剣の光 智と力
出雲に実る 豊穣の歌
namaḥ sarvatathāgatānāṁ apratihata-jñānābhiṣekebhyaḥ oṁ ca le cu le cundī svāhā
Draco Rex Nanda et Draco Rex Upananda
Raging waters cover the mountains,
Crimson eyes that seize the maiden,
A god’s voice, sword in hand,
A prayer’s light to guard the fields.
namaḥ sarvatathāgatānāṁ apratihata-jñānābhiṣekebhyaḥ oṁ ca le cu le cundī svāhā
Draco Rex Nanda et Draco Rex Upananda
Orochi falls, the rains descend,
Dragon Kings summon clouds above,
The sword shines with wisdom and might,
Izumo blossoms in a song of abundance.
namaḥ sarvatathāgatānāṁ apratihata-jñānābhiṣekebhyaḥ oṁ ca le cu le cundī svāhā
Draco Rex Nanda et Draco Rex Upananda
गुणस्य त्रिमूलम्
adix triplex qualitatis
The Three Roots of Virtue
福はただには来ず 徳より芽を出す
願い求むるだけでは 幸は結ばれぬ
徳なき者は 福に出会えず
徳を積む者は 無尽の幸を得る
namo saptānāṁ
samyaksaṁbuddha koṭīnāṁ tadyathā
oṁ cale cule cundī svāhā
如来の御前に 功徳を蒔け
正法の光に 功徳を蒔け
聖衆の中に 功徳を蒔け
三善根こそ 幸の道なり
namo saptānāṁ
samyaksaṁbuddha koṭīnāṁ tadyathā
oṁ cale cule cundī svāhā
गुणस्य त्रिमूलम्
सुखं स्वयमेव न आगच्छति; गुणात् प्ररोहति । केवलं कामना एव सुखं न लभ्यते। गुणहीनाः सुखं न प्राप्नुवन्ति। गुणसञ्चयिनः सुखं प्राप्नुयुः अनन्तम्।
तथागतस्य पुरतः पुण्यं वपतु।
सत्यधर्मप्रकाशे पुण्यं वपतु।
पवित्रजनेषु पुण्यं वपतु। गुणमूलत्रयं सुखमार्गः |
तथागतस्य पुरतः पुण्यं वपतु।
सत्यधर्मप्रकाशे पुण्यं वपतु।
पवित्रजनेषु पुण्यं वपतु।
Radix triplex qualitatis
Felicitas non per se venit; ex qualitate germinat. Desiderium solum felicitatem non affert. Qui virtute carent felicitatem non assequuntur. Qui virtutes accumulant felicitatem infinitam consequuntur.
Mercitum coram Tathagata offerat.
Mercitum in luce veritatis et iustitiae effundat.
Mercitum in populum sanctum effundat.
Tres radices virtutis sunt via ad felicitatem.
Mercitum coram Tathagata offerat.
Mercitum in luce veritatis et
iustitiae effundat.
Mercitum in populum sanctum effundat.