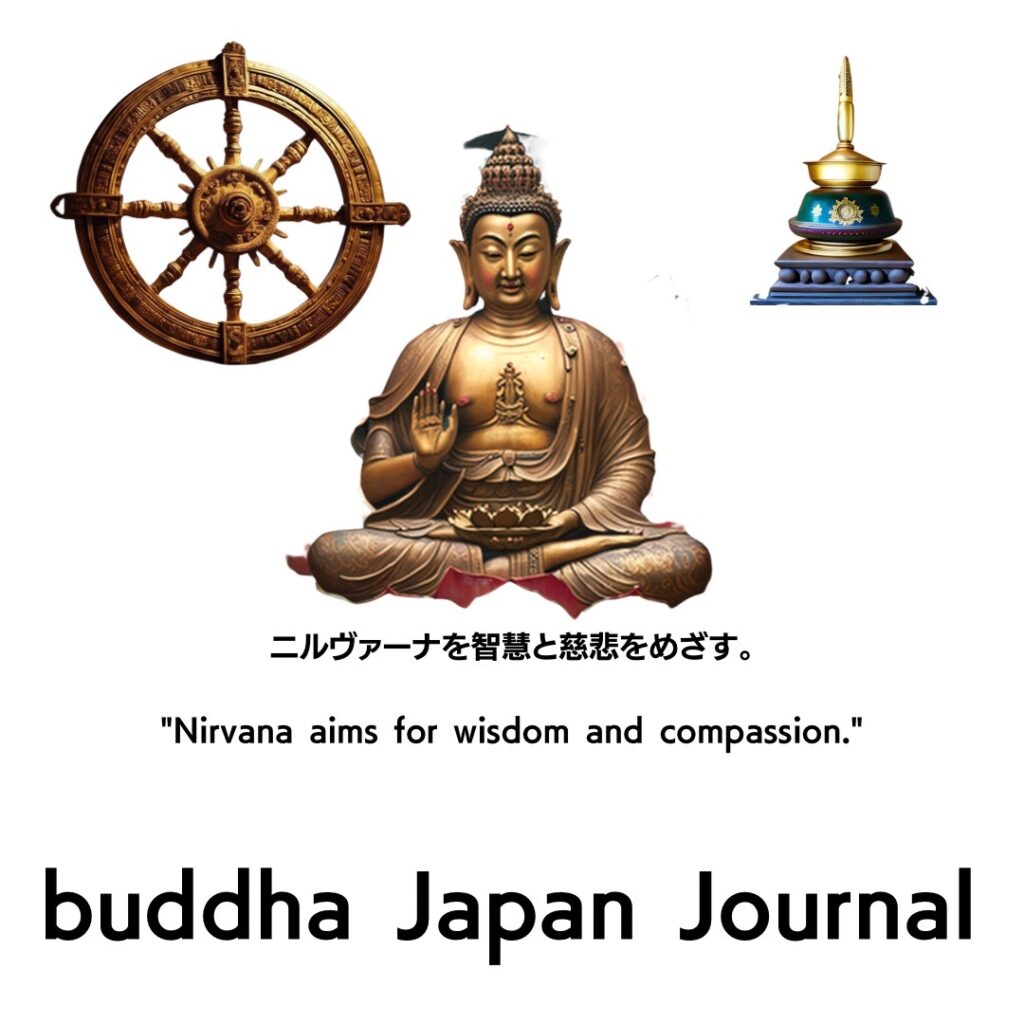ただ苦しみ悩みを解決させるだけではダメなのである。解決すると同時に、その
ひとを向上させるのでなければならない。また、向上することによって解決すると
いう場合もある。これが、正しい瞑想なのである。
だから、本当の瞑想は、「いま苦しんでいる問題の解決」からはじまるので
ある。
瞑想はゴータマーブッダがさいごに到達されたように、すべての存在から超越し
解脱するのであるが、超越・解脱する前に、現実を自由自在に処理し解決するだけ
の力を持たねばならない。その力を持たずして、超越とか解脱とかいったって、そ
れは一種の「逃避」に過ぎない。その力を持つ瞑想法が「欲界定」と「第二の段
階」の瞑想なのだ。
が、ここでまちがってはならないのは、この力を持つことが、ただたんに自分の
欲望を思うままにとげるということではないということである。yこの力を持つこと
によって、自分の望むことがその通り実現されることもあるし、バカげた野望・欲
望のとりこになって、いたずらに苦しんでいるおろかさに突然気がつき、夢からさ
めたひとのようになる場合もある。
どちらにしても、すばらしいことではないか。
瞑想の原点としてのヨーガ
瞑想は、インドにおいて非常に古くからおこなわれていた。それは、インド民族
の歴史とともにあったといってよい。
瞑想に関する文献は、ヴェーダ、ウパニシャッドの時代(紀元前一〇〇〇年~六
〇〇年)にまでさかのげって、目にすることができる。そのころから、すでに、瞑
想は、インド特有の身心修練の道として、修道者必修の行法とされていたのであ
る。
それは、ヨーガあるいは三昧あるいは禅とよばれた。
日本では、ヨーガというと、一般には、体操の一種のように思われているようで
あるが、それは元来、瞑想を主とするもので、体操は瞑想を助ける肉体の調整法だ
つたのである。
さきに述べたように、ブッダもまた当時の修道者のならわしにしたがってヨーガ
の瞑想を修行せられたが、それには満足できず、さらにすすんでブッダ独特の(智
慧の)瞑想を完成れたのである。ここでは、伝統的なヨーガの瞑想について、か
んたんに述べよう。
ヨーガにおける心の綜制
ヨーガ修行者の聖典ともいうベキゝ『ヨーガースートラ』によると、瞑想における
精神集中への心理的過程を、四つの段階に分けている。
割感・凝念・静慮・三昧である。
このなかで、凝念・静慮・三昧の三つの段階を一括して、「綜制」といっている
が、もちろん、実際の修練の上では、以上の三つの段階の一つゴつが独立している
のではなくて、連続的に進行するわけである。
ところで、いったいヨーガとはなにかというと、『ヨーガースートラ』はつぎの
・ように定義している。「ヨーガとは心のはたらきを抑滅することである」。
また『ヨーガースートラ』より古い文献である『ガターウパニシャッド』では、
「ヨーガとは五つの知覚器官を不動に執特することである」と述べている。
つまり、何らかの精神集中法によって、心の本体であるとりとめもない動き
を、しっかりと抑制することがヨーガであるのです。そして、それを修練して
いく方法がヨーガ行法なのであります。
これを現代的に分り易く表現すれば、我々の日常生活における意識の動きを
抑制していくことによって、自己本来の姿を見つけ出していこうとすることが
ヨーガであり、それを求めて修練していく方法がヨーガ行法なのであります。
『ヨーガースートラ』の中では、瞑想という精神集中法によって心の働きを制していく心理的過程が、詳細に分析的に述べられています。そして、このよ
うに瞑想を中心とした心理的なヨーガが、ラージアーヨーガとよばれるものな
のです。そして、この精神集中へ深まっていく心理的過程が、段階的に制感・
凝念・静慮・三昧と分けられているのであります