活性酸素とイチョウ葉エキス
二億五千万年を生き抜いた力
イチョウの樹の秘密

活性酸素の恐ろしさを、前に説明した。
ガン・心臓病・脳卒中・糖尿病など、生活習慣病 (成人病)の最大の原因となるものが、この活 性酸素だといわれている。
いや、いまや、生命体の老化の原因が、活性酸素によるものだといわれているのである。
ショウジョウバエというハエがいる。 成虫となってから約二十四時間しか生きていないので、よ く、遺伝の実験に使われている。 このハエが、どうしてこんなに生命が短いのか、その原因が最近 わかった。 それは、このハエは、生まれつき、活性酸素を防ぐ酵素を持っていないのである。その ために老化がかくも速く進んで、寿命が短いのだという。
この一つのことだけで、活性酸素の恐ろしさがわかると思う。
だから、われわれが、健康長寿を願うならば、まず、この活性酸素を防がねばならないのである。 幸いにも、人間は、ショウジョウバエと違って、活性酸素を防ぐ酵素を持っている。これを「スー
バー・オキサイド・ディスムターゼ」 (SOD)という。だが、このSOD発生装置も中年になると 衰えてしまって、十分に活動しなくなる。 四十歳を過ぎると急激に減少してしまって、五、六十歳 になると、ほとんど機能しなくなる。つまり、生活習慣病 (成人病の発生と、正比例するのであ
どうやって、活性酸素を防いだらよいのか?
その参考になるのが、植物である。
というのは、この恐ろしい活性酸素は、人間の体の中にだけ発生するのではないからである。 意 外のようだが、植物のほうが、人間の何倍もの活性酸素を発生させる危険にさらされているのである。 ご承知の通り、植物はその葉の中でブドウ糖をつくっている。 植物の緑の葉の中には、葉緑体と いう装置を持つ細胞工場がある。 植物はこの工場で、炭酸を材料に、ブドウ糖をつくるのである。
そのエネルギーは、太陽からとり入れる。 原料である炭酸は、大気中の二酸化炭素であり、これを根 から吸いあげた水に溶かせば原料となる。 これが、植物の「光合成」と呼ばれるメカニズムである。 光合成の過程では酸素が発生するので、葉緑体内部には、高濃度の酸素が多量にある。 高濃度の 酸素は、当然、強い活性酸素の材料となる。 活性酸素が発生したら、 植物も人間と同様、死んでしう。
どうするか?
ホット 植物は、自分の生命を守るために、ちゃんと、活性酸素除去の物質を持っているのである。この 物質を持っていない植物は、とうの昔に活性酸素のために絶滅して、姿を消してしまっている。いま、地球上に存在している植物は、みな、大なり小なり、この物質を持っているのである。
それは、フラボノイドという物質である。
フラボノイドは、葉の表面や種に存在して、活性酸素を除去する役目をはたしている。 そして、 非常に重要なことは、このフラボノイドの活性酸素除去の効力は、人間にも同じような効力を発揮 するということである。だから、われわれは、植物からこのフラボノイドを採って、 使えばいいわ けである。
植物はどんな植物でもみなフラボノイドを持っているから、どの植物でもいいわけだが、その効 力の高いものもあれば、低いものもある。 フラボノイドの種類は非常に多く、干のケタでかぞえら れるが、高等植物ほど、その種類が多い。
中でも、イチョウの葉のフラボノイドは、他に類を見ないほど強力である。
イチョウの樹は、生きた化石と呼ばれている。 二億五千万年の昔から、地球上に生き続けている からである。 その生命力の強さは、原爆投下後のヒロシマの廃墟の中で一番早く芽を吹いたと伝 えられているほどである。
イチョウの葉には、十種以上のフラボノイドが含まれているが、その中にイチョウ特有のものが 四種もあるのである。
このイチョウ特有のフラボノイドは、「二重分子フラボノイド」と呼ばれ、二個のフラボノイドが 重なった形になっている。
イチョウの葉が緑から黄に変わる時期に採取して、そこから抽出したエキスは、二重分子フラボノイドをはじめとするフラボノイドの豊庫である。
イチョウの葉に含まれる主なフラボノイドは、次の通りである。
ケルセチン・ラムノグリコシド」
ケンフェロール・ラムノグリコシド
ケンフェロール
イソラムネチン
ギンケチン
イソギンケチン
フラボンが二つ重なった、より強力な二重フラボン
ビロペチン
シアドピチジン
このイチョウの葉のフラボノイドの効用は、ドイツを起点として、スイスやフランスに、医薬品として広まっている。
ドイツでは、医薬品の適応症として、
◎めまい、頭痛、耳鳴り、記憶および集中力薄弱、脳血液循環不全による思考力の低下
脳卒中および脳挫傷の後遺症
◎血行不良による聴力および視力の低下
動脈硬化による腓腹筋のけいれん性疼痛
◎組織に対する血液供給不足による感覚麻痺、冷覚、足指蒼白
◎高年齢者におけるニコチン濫用および糖尿病による動脈血液循環不全
があげられ、医師によって臨床に用いられているのである。
フランスでも、だいたい同じような適応症があげられている。
◎脳循環不全およびそれに伴う機能障害(めまい、頭痛、記憶喪失、知能低下、運動障害、感情お よび性格混乱)
◎末梢血管障害から!!
細血管脆弱
下肢の動脈炎とその合併症 レイノールズ氏病、肢端知覚異常、肢端紅色チアノーゼ、
◎循環が原因となる神経感覚症状、特に眼科および耳鼻咽喉科領域におけるものほかに、フラボノイドの作用として、フランスにおいても、ドイツにおいても、活性酸素 フリーラジカル” を捕捉 除去し、過酸化脂質形成の予防および減少が認められてい
ビールの話
ヨーロッパではれっきとした医薬品で、ここ数年来、その売上高は全医薬品のトップにのし上っ ている。
十年ほどの間に三十倍にも達したという。たいへんな人気である。
アメリカでは一九八九年に健康食品として発売され、急成長している。 わが国でも、ごく最近、 健康食品として登場している。
イチョウという樹は非常におもしろい植物で、地球上に姿をあらわしたのは、約二億五千万年前、 古生代といわれている。中生代、ジュラ紀のちょうど恐竜が栄えていたころには、十五種類ものイ チョウの仲間が森林をつくっていた。 その後のたび重なる地球の大変動で大部分のイチョウは絶滅 してしまったが、ただ一種のイチョウだけが、 その危機を乗り越えて生き残った。 それがいま、わ れわれが街かどなどで見かけるイチョウなのである。
したがって、イチョウは分類上、仲間のいない一属一種の植物なのである。
二億五千万年にわたる地球の大変動にたえ抜いて生き残ったおどろくべき生命力の秘密がいま、 しだいに解明されつつあるのだが、おもしろいことに、日本産のイチョウが、活性酸素除去に一番、 効力があるという。欧米に向けて毎年、大量に輸出されている。
ここで知っておかねばならぬことは、イチョウの葉が活性酸素の除去に役立ち、脳血管や循環系 の調節に効果があるからといって、手あたりしだいに葉を採ってきて、煎じて飲んでも、その効
果は期待できないということである。
イチョウの葉のフラボノイドはタンパク質と結合して、分子量が一、二万と大きくなっている。 人間は、五千以下でないと吸収できない。 医薬品や健康食品に用いられるエキスは、特許技術によっ 四千以下におさえられているのである。
わたくしは、この特許技術によって製造されたイチョウ葉エキスを、朝晩、 適量、摂っている。 光和食品株式会社の総合ビタミン・ミネラルサプリメントには、一日量のイチョウ葉エキスが入っ ているので、このサプリメントを飲むだけでよいわけだが、 重複しても害はないし、少し多いほう が効果があってよいだろうと思うので、わたくしはそうしている。
紫外線の害は非常に恐ろしい。
スポーツその他で太陽を浴びるときには、外用の紫外線よけクリームを顔や手足に塗ると同時に、 イチョウ葉エキスを増量して内用し、その害を防ぐように心がけてほしいものである。
Active oxygen and ginkgo leaf extract
The power that has survived 250 million years
The secret of the ginkgo tree
I explained earlier how scary active oxygen is.
This active oxygen is said to be the biggest cause of lifestyle-related diseases (adult diseases) such as cancer, heart disease, stroke, and diabetes.
In fact, it is now said that the cause of aging in living organisms is active oxygen.
There is a fly called Drosophila melanogaster. Because they only live for about 24 hours after becoming adults, they are often used in genetic experiments. I recently discovered the reason why this fly has such a short lifespan. This is because these flies are not born with an enzyme that prevents active oxygen. It is said that because of her, aging progresses so quickly and lifespans are short.
I think this one thing alone will help you understand how scary active oxygen is.
Therefore, if we wish to live a long and healthy life, we must first prevent this active oxygen. Fortunately, humans, unlike fruit flies, have an enzyme that prevents free radicals. This is
It is called bar oxide dismutase (SOD). However, this SOD generator also declines in middle age and becomes inactive. After the age of 40, it decreases rapidly, and by the age of 50 or 60, it is almost no longer functional. In other words, it is directly proportional to the occurrence of lifestyle-related diseases (adult diseases).
How can we prevent active oxygen?
Plants are a good reference for this.
This is because this terrifying active oxygen does not only occur within the human body. It may seem surprising, but plants are exposed to the danger of producing many times more active oxygen than humans. As you know, plants make glucose in their leaves. Inside the green leaves of plants are cell factories containing chloroplasts, a device she calls. In this factory, plants use carbonic acid to make glucose.
That energy is taken from the sun. Carbonic acid, which is the raw material, is carbon dioxide in the atmosphere, and when it is dissolved in water sucked up from the roots, it becomes the raw material. This is the mechanism called “photosynthesis” in plants. Oxygen is generated during the process of photosynthesis, so there is a large amount of highly concentrated oxygen inside the chloroplast. Highly concentrated oxygen naturally becomes a material for strong active oxygen. If active oxygen is generated, plants will die just like humans.
what to do?
Hot Plants have substances that remove active oxygen in order to protect their own lives. Plants that do not have this substance have long since become extinct due to active oxygen and have disappeared. All plants existing on earth today have this substance, to a greater or lesser degree.
It is a substance called flavonoid.
Flavonoids exist on the surface of leaves and seeds and play the role of removing active oxygen. What is very important is that this flavonoid’s ability to remove active oxygen also has a similar effect on humans. Therefore, we can collect flavonoids from plants and use them.
All plants have flavonoids, so you can use any plant, but some have high potency and others have low potency. There are so many different types of flavonoids that they can be counted in numbers, and the higher the plants, the more types there are.
Among them, the flavonoids in ginkgo leaves are uniquely powerful.
The ginkgo tree is called a living fossil. This is because he has been living on earth for 250 million years. Its vitality is so strong that it is said that it was the first to sprout among the ruins of Hiroshima after the atomic bomb was dropped.
Ginkgo biloba leaves contain more than ten types of flavonoids, of which four are unique to ginkgo biloba.
This flavonoid unique to ginkgo is called a “double molecule flavonoid,” which consists of two overlapping flavonoids.
The extract extracted from ginkgo leaves collected when they turn from green to yellow is rich in flavonoids, including double-molecule flavonoids.
The main flavonoids contained in ginkgo leaves are as follows.
Quercetin rhamnoglycoside
Kaempferol rhamnoglycoside
kaempferol
isorhamnetin
Ginkechin
sea anemone ketin
A more powerful double flavone with two flavones stacked on top of each other.
Vilopetin
Cyadopitidine
The effects of the flavonoids in ginkgo leaves have spread from Germany to Switzerland and France as a medicinal product.
In Germany, as an indication for pharmaceuticals,
◎Dizziness, headache, tinnitus, poor memory and concentration, decreased thinking ability due to cerebral blood circulation failure
Aftereffects of stroke and brain contusion
◎Deterioration of hearing and vision due to poor blood circulation
Spasmodic pain in the gastrocnemius muscle due to arteriosclerosis
◎Sensory numbness, cold sensation, and pale toes due to insufficient blood supply to tissues
◎Arterial blood circulation failure due to nicotine abuse and diabetes in the elderly
are used clinically by doctors.
In France, roughly the same indications are listed.
◎Cerebral circulation failure and related functional disorders (dizziness, headache, memory loss, decreased intelligence, movement disorders, emotional and personality confusion)
◎From peripheral vascular disease!!
small vessel fragility
Arteritis of the lower extremities and its complications: Reynolds disease, acroparesthesia, acrocyanosis,
◎In addition to neurosensory symptoms caused by circulation, particularly in the fields of ophthalmology and otorhinolaryngology, flavonoids have been shown to scavenge and eliminate active oxygen free radicals and reduce the formation of lipid peroxides, both in France and Germany. Prevention and reduction are recognized.
beer story
It is a well-established drug in Europe, and for the past few years, its sales have risen to the top of all drugs.
It is said that the number has increased 30 times in about 10 years. It’s very popular.
It was launched in the United States as a health food in 1989 and has been growing rapidly. In Japan, it has recently appeared as a health food.
The ginkgo tree is a very interesting plant that first appeared on Earth about 250 million years ago, during the Paleozoic era. During the Mesozoic and Jurassic eras, when dinosaurs were flourishing, forests were created by as many as 15 species of butterflies. Most of the ginkgo species became extinct due to the many cataclysmic changes that followed, but only one species, the ginkgo biloba, survived the crisis. These are the ginkgo trees that we now see on our street corners.
Therefore, ginkgo biloba is classified as a type of plant in a genus with no relatives.
The secret of the amazing life force that has survived the earth’s cataclysmic changes over the past 250 million years is gradually being revealed, but interestingly, Japanese ginkgo biloba has been shown to be effective in removing active oxygen. It is said that it is effective. Large quantities are exported to Europe and America every year.
What you need to know here is that even though ginkgo leaves are useful in removing active oxygen and are effective in regulating cerebral blood vessels and the circulatory system, it is important to pick up as many leaves as you can and make a decoction. Even if you drink it, its effects
The results are unpredictable.
The flavonoids in ginkgo leaves combine with proteins and have a molecular weight of 10,000 to 20,000. Humans cannot absorb anything less than 5,000. The amount of extracts used in medicines and health foods is kept below 4,000 using patented technology.
I take an appropriate amount of ginkgo biloba extract produced using this patented technology in the morning and evening. Kowa Foods Co., Ltd.’s multivitamin/mineral supplement contains a daily dose of ginkgo biloba extract, so you only need to take this supplement, but there is no harm in taking more than one, and a little more is more effective. I am doing this because I think it would be good to have one.
The damage caused by ultraviolet rays is very scary.
When you are exposed to the sun for sports or other activities, you should apply external UV protection cream to your face, hands and feet, and at the same time increase the amount of ginkgo biloba extract and use it internally to prevent the damage.
http://cyber-price.com/buddha/
Buddha Japan Journal
Buddha Japan journal
日本の仏教を発信しますSend Japanese Buddhis
Buddha 2Japan journala
日本の仏教を発信しますSend Japanese Buddhis sサイト
大日如来の智慧を表現した「金剛界」 .一印会 “Kongokai” expressing the wisdom of Dainichi Nyorai.Ichiinkai
胎蔵界曼荼羅 たいぞうかい Womb Realm Mandala Taizokai
デジタル 健康 PC カメラ 家電
cyber-price
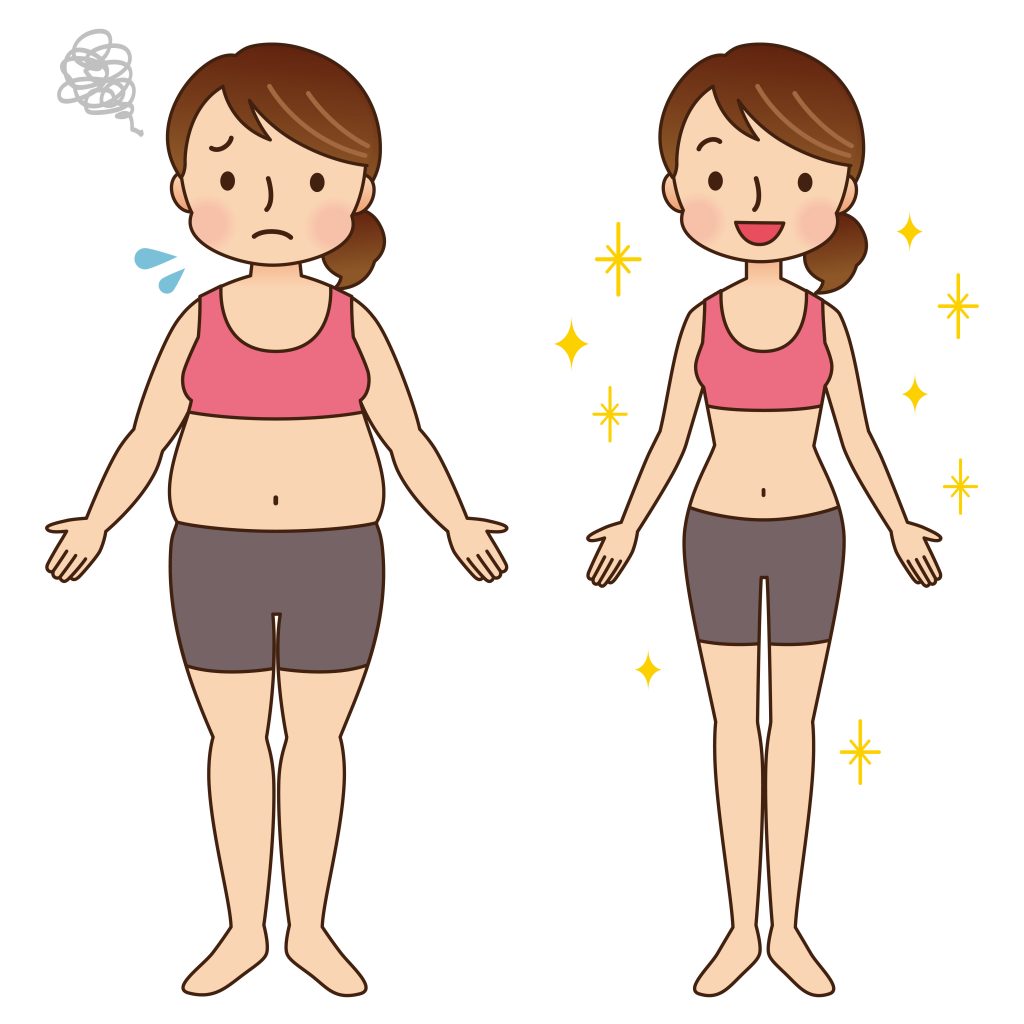

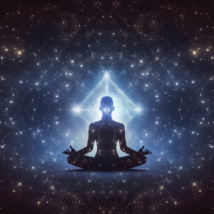
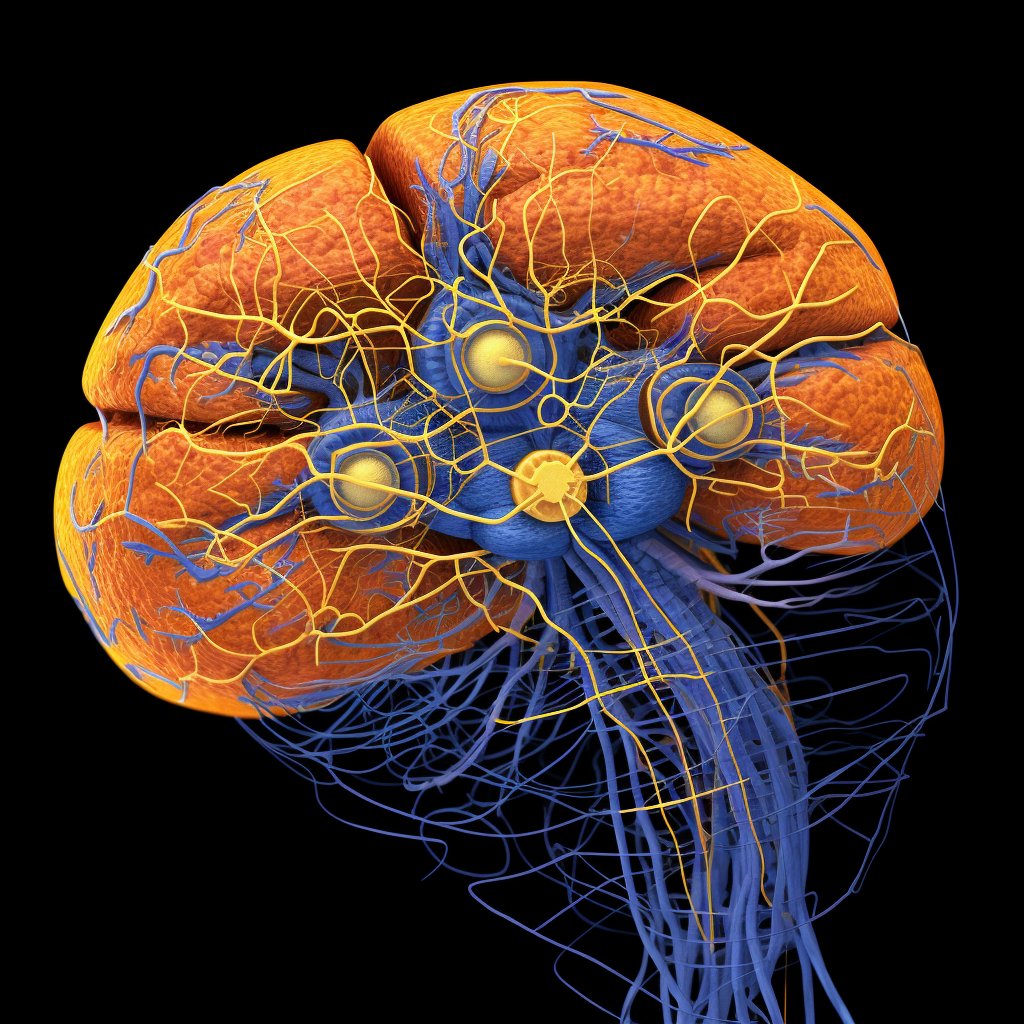

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/169d1732.20fb4103.169d1733.016426e2/?me_id=1209304&item_id=10085049&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenergy%2Fcabinet%2F03153809%2Fkennkousyokuhinn5%2F07952770%2Fimgrc0091824844.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/39830849.e2efdc2b.3983084a.8c567d11/?me_id=1390412&item_id=10005052&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkwrydrug%2Fcabinet%2F10196584%2Fimgrc0122434572.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)



